市田柿とは

市田柿は、2016年に地理的表示(GI)保護制度に登録された南信州を代表する特産品です。
あめ色の果肉と小ぶりで品のある外観、もっちりとした食感と口に広がる上品な甘さは、市田柿ならではです。
ビタミンA、食物繊維などの栄養素も豊富に含み、また渋柿の中に含まれる渋味成分(タンニン)がポリフェノールの一種であることから、スーパーフードとしても注目を集めています。
市田柿の歴史と味わい
「市田柿」というのは現在の下伊那郡高森町の市田地域で栽培されていたことから名前のついた渋柿の品種名です。その栽培の歴史は500年以上といわれ、これを干し柿にしたものも「市田柿」と呼びます。干し柿は一口大で食べやすく、鮮やかなあめ色の果肉をきめ細かな白い粉が覆い、もっちりとした食感と上品な甘味があるのが特徴。自然の甘さをもつドライフルーツであると同時に、高級和菓子にも位置づけられています。
南信州の象徴「柿暖簾」

秋の紅葉が盛りを迎え、山々や庭先の木々が緋色・柿色になるころ、「市田柿」は収穫を迎えます。農家できれいに皮むきされた「柿のれん」は、紅葉の景観にいっそうの美しさを添えます。
江戸時代後期、当時の下市田村(現・下伊那郡高森町)に“焼柿”と称した原木があり、その名のとおり焼いて甘くして食べられていました。その“焼柿”が干して食べても美味しいことが広く知られ、大正時代に村の篤農家たちが「市田柿」と称して出荷をしたのが始まりです。それから、天竜川沿岸を中心に渋柿への接木によってしだいに普及していきました。1952年に長野県が奨励品目に取り上げ、優良系統選定、優良母樹指定、干柿加工技術試験研究を繰り返し、果樹栽培の一環として全国に名だたる特産品となりました。
GI(地理的表示)に登録

市田柿は長野県初のGIに登録されています。GIとは生産地と結び付いた特性を有する農林水産物食品の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。
つまり、市田柿は、この地域ならではの食品として国からお墨付きをいただいています。
地域団体商標の取得
わたしたちの地域資源をブランドとして磨き上げ、地域の魅力や実力を地域の外に強くアピールする“地域ブランド”(地域団体商標)。JAみなみ信州と下伊那園協が共同出願した『市田柿』が2006年10月、県下初の地域ブランドに認定されました。全国で知名度が高まりつつあり、今や海外、台湾にも輸出されて注目を集めています。
栽培から取り組む市田柿づくり
栽培

古くから冬の保存食として用いられ、お正月の「歯固め」として食べられていた市田柿。その栽培と加工は伝統的な手法で続けられていますが、近年その価値とブランドが認められるにつれて、より品質の良い干し柿を消費者に供給する必要が出てきました。
品質の良い干し柿を作るには、加工技術はもちろん、良い原料柿を用いることがなにより重要です。そして、良い原料柿を作るには、柿の収穫を終えて来年の収穫までの、栽培管理が欠かせません。施肥やせん定、摘果などの管理が充実している園では、糖度が増し、優れた果実ができます。一方、管理がゆき届かず、葉や果実に病害虫の被害を受けた木の柿は、糖度が低く美味しい干柿になりません。また、緑色が残る熟度の若い柿を収穫して加工すると、渋味が残るなどの品質低下が発生しやすくなります。
樹勢に応じた適切な施肥とせん定、摘果などの管理。病気や虫の発生を防ぎ果実を健やかに育てるための薬剤防除。そして収穫は急がず樹上で適熟になった柿を加工すること。こうした農家の努力とJAの指導がブランドにつながっています。
収穫

11月上旬から中旬にかけ、原料の生柿の収穫が行われます。この時、柿農家は畑での収穫と家での皮むき作業を平行して行うため、とても忙しい時期です。全体が濃いオレンジ色になりよく熟した柿を収穫します。
柿むき・のれんづくり

柿の皮をむいてのれんに吊るし、色のよい干し柿に仕上げるため、硫黄くんじょうを行います。皮むき機械で1日におよそ800kgの柿をむきます。皮むき期間は量が多い農家だと10日間以上かかり、のれんごとの仕上がり時期も違うため、あらかじめ一つひとつの柿のれんの重量をチェックし、はざおろし(のれんから柿をはずすこと)の目安とします。
乾燥

ハウスや家の2階などで1ヶ月程乾燥します。乾燥期間中、湿気が多いとカビが発生しやすく、乾燥しすぎても渋味が抜けにくくなってしまいます。天気をみながら窓を開閉したり、のれんの間隔を調節したりと、適切な温度と湿度を保つよう工夫します。
飯田下伊那地方は、東西を中央アルプスと南アルプスに挟まれた「伊那谷」と言われ、その間を天竜川が流れています。天竜川からは、晩秋から冬にかけ毎朝のように川霧が発生します。この地域の冬はとかく乾燥しがちなのですが、この天竜川から湧き上がり段丘をのぼる霧が、干し柿を一気に乾かさないようにする自然の“加湿器”となり、市田柿独特の「もっちり、ねっとり」とした食感を生み出しているといわれます。この地域ならではの自然の恵みです。
柿もみ・天日干し

皮むき時の35%程の重さになるまで乾燥したら、のれんから下ろして、1個1個の乾燥程度を見ながら柿をもみます。水分が多い場合は、写真のように天日に干して調整します。柿もみは、柿の中心部の水分を押し出してシワのないやわらかな干し柿をつくり、きめ細かい粉を出させるための大事な作業。現在は、ドラム式の機械で行われています。 3〜4回程、ていねいな柿もみと寝せ込みを繰り返すと、白い粉(ブドウ糖)に覆われた干し柿が出来上がります。 微妙な調整が要り、干し柿農家の経験が発揮される作業です。
出荷

完成した干し柿は、農家にて化粧箱・トレー等への包装作業を行い、JAの集荷場にて内部検査を行ったうえで全国へ出荷されます。
また、バラの状態で集荷した干し柿はJAの「市田柿工房」にて選果・リパックを行います。 (写真は700g・1.2㎏化粧箱)
以上の記事は、長野県みなみ信州農業協同組合から情報提供を受けています。
詳細は下記までお問い合わせ下さい。
TEL. 0265-56-2300 FAX. 0265-56-4400

「市田柿」命名100年 その名は全国へ、世界へ。
出典:2020年11月22日付 中日新聞長野版会員限定記事
晩秋から初冬の候、南信州(飯田下伊那地方)の風物詩といえば、農家の軒先やハウス内を鮮やかに彩る「柿のれん」。皮をむかれ、何列にもつり下げられた渋柿はじっくりと乾燥され、地域ブランドの高級干し柿に仕上がっていく。二十四日にJAみなみ信州の出荷が始まる「市田柿」。今年は命名百年目に当たる。
さて、生市田柿のことを果樹百科事典や研究書物で調べてみる。概要だが「約六百年前から高森町(旧市田村)下市田付近に多くあった渋柿」「一九二四(大正十三)年に開いた『柿品種調査展覧会』では、優良品種の中に焼柿(やきがき)(別名市田柿)として紹介され、豊産で干し柿の品質が高い」ことなどが分かった。
焼柿の名は、生果を焼いて食べると非常に美味であることに由来するとされる。食文化の研究書に「干し柿は市田柿ではなく『やきがき』という自生の柿を使う」という農家の話が載っていたこともあり、焼柿は生市田柿とは別品種の可能性が高い。
高森町発行の「市田柿のふるさと」(二〇一〇年九月の第二改訂版)には、下市田に江戸時代に創建された伊勢神社境内にあった焼柿の古木が市田柿の原木と紹介され、この場所には「市田柿原木の地」と刻んだ石碑も立っている。
生市田柿が広まる以前、飯田下伊那地方で干し柿にされていたのは飯田市三穂立石に由来する「立石柿」だった。生市田柿より小ぶりな渋柿で、串にさして干した縁起物の串柿は江戸時代には米に代わる年貢として納められていた。串柿づくりの伝統は三十年ほど前まで残っていたが、今では市田柿にその座を完全に譲った。
旧下市田村一帯の農家は立石柿のほか焼柿も多く栽培。食味の良い焼柿を立石柿に接ぎ木して生市田柿の栽培が広まっていったのではないだろうか。
一九二一(大正十)年、村の壮年団は今でいう地域おこし事業で「焼柿」から「市田柿」への改称に取り組んだ。その年から、干し柿商品は「市田柿」として、東京や名古屋の市場に送られ、現在の隆盛につながっている。
六五(昭和四十)年には飯田下伊那地域で生産される干し柿ブランド名を「市田柿」に統一。大型乾燥施設の導入や品質検査体制の整備などもあり、徐々に商品価値を高めた市田柿は二〇〇六(平成十八)年に県内第一号の「地域団体商標(地域ブランド)」に認可された。さらに一六(平成二十八)年の地理的表示(GI)保護制度への登録により、全国はもとより、世界にその名を広げている。
2020年11月22日 05時00分 (11月22日 13時58分更新) 中日新聞長野版会員限定記事から。

(この柿の写真は2020年10月撮影で市田柿と関係がありません)

 ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています
ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています
 みなみ信州農業協同組合
みなみ信州農業協同組合






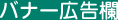

















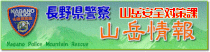
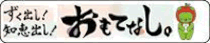



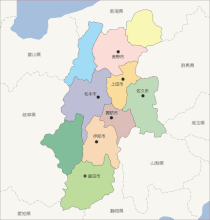






コメントをお書きください