100年の歴史ある「天竜舟下り」が、コロナの影響で幕引き。
長野県飯田市の天竜川で観光船「天竜舟下り」の運航を手がけるバス会社「信南交通」(飯田市)は、舟下り事業から2022年3月末で撤退する方針を明らかにしました。
新型コロナウイルスの影響でバス事業の収益が大幅に落ち込んでいるためで、赤字が続く舟下り事業を手放し、バス事業の再生を急ぐ。舟下りの事業を引き継ぐ企業探しは難航しているそうです。
天竜川の遊覧舟下りは100年を超える歴史があり天竜舟下りは船頭でもある船大工が木造和船を建造し、手こぎで急流を下るもので、伝統の技を含め、飯田市民俗文化財に指定されています。下段に紹介しています。
物流手段として始まった舟下りで、1960年代から観光船として運航。
飯田市の天竜川約6キロを木造船で下る爽快感などが人気となり、飯田市に残る記録では02年度のピーク時は約13万6000人が乗船。
その後は減少し、19年度の6万1000人から21年度には1万8000人まで落ち込み、赤字も増大。
近年では、コロナ禍に加えて、かき入れ時の夏場の増水、渇水などで運航できない日も増えていたそうです。
天竜舟下りは昭和20年代から40年代初めまで、一時、吉川建設(同市)が株式会社化して運営していましたが、2011年に浜松市での天竜川下り船の転覆事故の影響で乗客が激減してしまい、信南交通が買収して再運営してきました。
同社長によると、「舟下りが地域観光にとって非常に大事だと重々承知しているが、私どもの力不足で運航できないのは申し訳なく思っている」と述べ、舟下り事業に携わる社員や船頭らは関連会社などへの配置転換を促す方針。
保有するバスの一部を売却したり、再雇用した運転手を減らしたりするなどしてきたが、「会社として存続できるかどうかの瀬戸際」として、バス事業の再生を優先し、舟下り事業から撤退することで地方金融機関と大枠合意したということです。
「天竜川の舟下り」飯田市民俗文化財指定
平成28年6月6日開催の飯田市文化財審議委員会から文化財指定の答申を受け、平成28年7月14日(木曜日)に開催された教育委員会定例会において、「天竜川の舟下り」を飯田市民俗文化財に指定することが決定しました。
天竜川の舟下りが指定された理由について、以下の四つの価値を見出すことができます。
1. 日本における観光川下り舟の草分けの一つであること
天竜川の舟下りは、江戸時代から続く天竜川での物資輸送の歴史を継承しつつ発展し、大正6年(1917)に遊覧専門の舟下りが開始されました。観光川下り舟としては、全国で6番目に歴史が古く、事業者の変更や戦争での中断はあるものの、およそ100年の歴史を有しています。
2. 操船・造船技術に地域的な特徴が認められ、その技術が継承されたこと
天竜川の舟下りに使われる舟は、設計図を使わず、船頭の長年の勘によって作られます。操舟技術も、マニュアルなどはなく船頭の先輩の動作を見て身体で覚えます。現在、全国的に合成樹脂製の舟が主流を占め、木造船の造船・操船技術が失われつつある中で、伝統的な木造船の造・操船技術を継承していることも天竜川の舟下りの価値ある点といえます。
3. 天竜川の舟下りが生んだ文化が存在すること
天竜川の舟下りには数多くの文人墨客(ぶんじんぼっかく)が乗船し、名勝天龍峡をはじめとする天竜川の景観を楽しみ、それを題材にした作品を数多く残しています。紀行文や短歌、日本画や映画の主題歌まで、天竜川の川下りによって生まれた文芸作品等は数多く、加えて、飯田といえば天竜川の舟下りが連想されるように、当地域を広く宣伝することになりました。
4. 名勝天龍峡を楽しむためのもっともすぐれた手段であること
国指定の名勝天龍峡と天竜川の舟下りは密接な関係にあります。遊覧船としての舟下りは、激流を下るスリルと鵞流峡(がりゅうきょう)や天龍峡の峡谷美を川面から眺めることを目玉としていました。昭和9年(1934)に出された文部省(当時)による名勝指定の説明にも川下り舟は記され、奇岩断崖とともに名勝天龍峡の価値のひとつとして位置づけられています。また、巌谷小波(いわやさざなみ、児童文学者)の紀行文では「是非とも舟で遊ぶべき所である」と舟下りの良さが強調されています。このように天竜川の舟下りは、名勝天龍峡や鵞流峡といった峡谷部をはじめ、伊那谷の変化に富んだ景観と天竜川の流れを安全にかつ存分に味わうことができます。
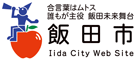
〒395-8501
長野県飯田市大久保町2534
Tel:0265-22-4511(代表)
メールでのお問い合わせはこちら
「文化財保護いいだ」
飯田市教育委員会事務局
文化財保護活用課
文化財保護係
Tel:0265-53-3755
Fax:0265-53-3756

 ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています
ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています





































コメントをお書きください