昨日12日、飯田市で「三六災害60年シンポジウム」が開かれました。
コロナで1年延期されていたものですが、出水期を控え、災害について改めて考える良い機会になりました。
シンポジウムでは、元国土交通省砂防部長から「天竜川上流域の降雨特性と地形」と題しての基調講演がありました。内容は、全国的に見れば、この地域は比較的降雨量の少ない地域であり、大雨の主要因は前線で、南部ほど降水量が多い。
地形との特性では、この地域を囲む山々や峠によって降雨が起きている。
三六災害では、前線の停滞と太平洋上の台風くずれの低気圧があり、南からの暖湿流が峠を越えて前線に供給され続け豪雨になったと分析しています。
パネルディスカッションでは、テーマ毎に以下の内容でした。
①三六災害を振り返る(経験談)
②備える(近年の異常気象や避難のあり方)
③伝える(未来へ伝えたい教訓など)
「三六災害を振り返り、近年の異常気象を踏まえ、命を守る行動を考える」。
平松晋也信大教授をコーディネーターに5人のパネリストが意見交換。
前大鹿村長の経験談、家族から聞き伝えている方の生々しい話が心に残りました。
小渋川の決壊や最大の悲劇と言われる大西山の崩壊などがありました。
また、災害への備えでは、正常性バイアスが避難行動につながらない。
「異常な事態に直面しながら、大したことにはならないだろ、自分は大丈夫だろう」と思い込み、危険や脅威を軽視しようとする。」
自助、共助、公助について、自助は、個人戦だけれど、共助は団体戦である。
団体戦は、あらかじめ作戦を考えることの必要性。地震発生時の避難と土砂災害の避難の違いもあります。
避難しやすい場所へ、安全な場所に早く逃げることが重要です。
60年が経過した今日、三六災害を知らない人が多くなっている中で、伝承の必要性と防災教育についても検討。
特に、子どもたちの防災教育とともに、教師向けにも必要である。
以上の記事は、参加した長野県箕輪町長のブログから引用転載し、再編集しています。
ご了承下さい。
文責:@ja0hle
三六災害とは
長野県の伊那谷は、西に中央アルプス、東に南アルプスに囲まれた美しい自然豊かな地域です。しかし、ときに美しい自然は、猛威を振るうことがあります。
昭和36年(1961年)、台風の接近と梅雨前線の停滞による激しい雨が伊那谷を襲い、伊那谷の各地で川の氾濫、土石流、地すべりが発生しました。何十年に一度か百年に一度くらいにしか起きないといわれるほどの大災害となりました。
家や田畑が土石流に押し流され、集落ごと水びたしになったり、土石流とともに無くなったりした集落もあります。三六災害による死者・行方不明者は136名、家屋の全壊・流失・半壊は1,500戸にも及びました。
伊那谷では1週間で年間平均雨量の3割を超える豪雨(飯田観測所:総雨量579mm)に襲われました。
被災箇所は1万箇所を超え、被災額は341億円(現在の価格換算で1224億円)。
国土交通省天竜川上流河川事務所では、三六災害50年実行委員会の声明を踏まえ、災害を語り継ぐ一助とするため、記録資料を地図情報化し、地域で幅広く活用されるための情報提供を行い、今後の防災・減災対策に役立てることを目的として「三六災害アーカイブス」として公開しています。
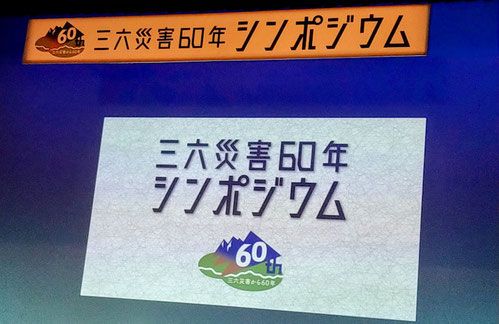
写真提供:長野県箕輪町長

写真提供:長野県箕輪町長
国土交通省 中部地方整備局天竜川上流河川事務所リンク先
リンクについては、三六災害アーカイブスへのリンクは自由です。トップページについては個別にリンクを張ることができます。 三六災害アーカイブ内の各ページにリンクされる場合は、そのページが三六災害アーカイブス内にあることが分かるように、必ず明記してください。下記URLは、「三六災害アーカイブス」へリンクしています。
お問い合せ先
国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
砂防調査課 三六災害アーカイブス
長野県駒ヶ根市上穂南7-10
電話:0265-81-6417
FAX:0265-81-6421

 ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています
ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています






































コメントをお書きください