袖がない防寒着。南信州木曽上松の「ねこ」。
「ねこ」とは、動物の猫のことではありません。
今回紹介するのは、信州の南部に昔から伝わる防寒着で、袖がなく、さっと羽織ることができて、背中から優しく身体全体をあたためてくれる信州木曽の厳しい冬を過ごす伝統的防寒着のことです。
「秘密のケンミンSHOW」で紹介されたこともあります。
この「ねこ」は、長野県の木曽地方の南木曽町と上松町で作られていて、「南木曽ねこ」と「上松ねこ」があり、形は似てるけれど町や作る家庭で違いがあります。
「南木曽ねこ」はネットなどでも販売されているのですが、「上松ねこ」は知る人ぞ知るなかなか手に入りにくい貴重なイッピンものです。
木曽の冬の防寒着『ねこ』を着物をほどいた古布をつかって手縫いで仕上げます。
冬前の手仕事。真綿をひろげてじんわりの暖かさを感じながら、自分だけのねこをつくりませんか。
昔は、養蚕が盛んだった信州です。南信州の養蚕農家の女性は、出荷できなかったお蚕(かいこ)さんの繭で真綿をつくり、着物をほどいた古布と「もめん綿と真綿」をつかい『ねこ』を家族のために作られたもので、現在でも家庭で作られているものです。
最初は、素材の着物から、表地と裏地の布選びと丈の長さを決めることです。
沢山の着物の生地から自分の好みの色や柄を選び、裏地と組み合わせる時間は一番ワクワクする時間かもしれません。
『ねこ』の特徴は驚くほど軽く、薄く、暖かく、肩が凝らないことです。
寒い日にセーターの上に羽織る上着のように、またはセーターの中にインナーのように着ることもできます。
布選びが終わるとまず針仕事です。
首周りと自分で決めた長さに布を裁断し、しつけをして、裏地と表地を縫い合わせ、両脇の布の始末をします。あっという間に2時間が過ぎてしまいます。
両脇を縫い上げたら、紐を作ります。そしてこの「ねこ」作りの一番の要が、
「もめん綿を敷き詰め、お蚕さんが作った真綿を広げる」という作業です。
次は、真綿を広げる作業です。
ほんの少しの真綿を、2人で端と端を持って伸ばすと切れずに薄く広がります。
もめん綿の上にこの少しの真綿が重なることで軽くてとても暖かい「ねこ」ができるということです。
また、縫って短くなってしまった糸と新しい糸を繋ぐ方法や、短くなって玉止めができない時の処理の方法など勉強になります。
今後の暮らしにも活かせられそうです。
次は、縫い方は和裁の「くけ縫い」というやり方です。
波縫いとは違い時間がかかるため、辛抱強く縫い上げていきます。
2~3時間で出来上がらなかったら、翌日、翌々日にして完成させる方が楽しみです。
自分で作った「ねこ」を背負うと嬉しい気持ちでいっぱいです。
手縫いで「縫えた」ということが自信につながり、自分で「縫える」という体験が今後生きていくうえで大切になってくるのではないかと感じます。
南信州木曽「ねこ」の半てんの作り方を紹介します。
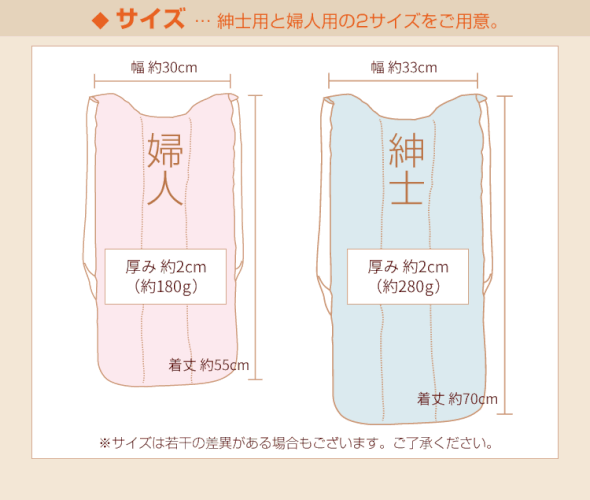
◆yahooショッピングに出店
お問い合わせ頂きました皆様、大変お待たせいたしました。
ぜひ、この機会にご利用下さい。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/nagiso-neko/

 ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています
ようこそ名古屋長野県人会へ
長野県で生まれた人
長野県で育った人
信州が好きな人が集っています






































コメントをお書きください